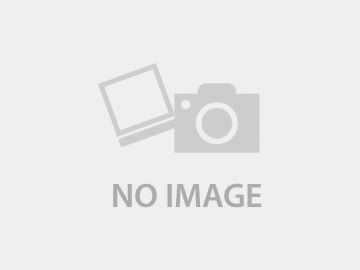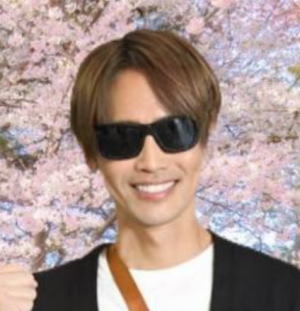社会の情報洪水の中、「健康のため」「将来の不安回避のため」と、私たちは知らず知らずのうちに生活や働き方を固くしがちです。しかし本当に心豊かな人生や、思いがけず健康を手に入れる秘訣は、もっと肩の力を抜いたアプローチにあるのではないでしょうか。本記事では、現実の体験や世界の多様な知恵を交えつつ、“楽しく働く”ことこそが幸せと健康の源泉である、という全く新しい視点を投げかけていきます。知識と実感が織りなす世界に、一歩踏み込んでみましょう。
健康を作る先入観の罠と“気にしすぎ”からの脱却
「毎年の健康診断が気になって仕方ない」「仕事中でもいつも体の不調に気を取られてしまう」。このような声を秋田県のローカルコミュニティで幾度となく耳にしました。筆者自身も、20代半ばのころ定期的に健康への不安に悩まされ、ネットで症状を検索しては余計に心配し、時に夜も眠れなくなる経験を持っています。
しかしあるとき、郷里のある年配農家の方が「健康って気にしすぎると逆にダメなんだよ」と笑って言う姿にハッとしたのです。その方は70歳を越えても、毎朝畑に出て土いじりを楽しみ、病院に行くのは年に一度程度。それでも周囲の同年代よりはるかに元気に見えました。「あまり細かく検査しすぎても、余計に心が重たくなるもんさ」と、素朴ながら本質的な言葉。
健康管理に“根を詰め過ぎる”こと自体がストレスとなってしまう――厚生労働省の研究でも度重なる不安感や過度な心配が心身症・免疫力低下にも繋がることは周知の事実です。考えてみれば、検診や人間ドックはあくまで「状態を知る」ための手段。そこで分かったことに一喜一憂しすぎるより、日常の中で「自分を観察して、楽しんでいるか」を意識することの方が長期的な心身の健康には欠かせません。
筆者の友人に、自宅でリズムやテンポを気にせずピアノと戯れる40代女性がいます。彼女は若い頃過食症や体調不良に悩んでいましたが、仕事や健康を意識しすぎるのをやめ、「朝少しでも音楽に触れる」ことを日課にしてから、驚くほど心身のバランスが良くなったと話しています。「健康・健康って気にすると逆に身体が受け身になって固まっちゃう。何より好きなこと、夢中になれることをちゃんと持ってると、体も機嫌がいいんだよね。」
医学的根拠だけでなく、現実の世界にはこうした実例が無数にあります。要するに「気にすればするほど健康を損なう」―この逆説を肝に銘じて、“毎日をどう楽しめるか”に思い切って舵を切ってみること。あなたの健康観に、少し風を入れてみてはいかがですか?
“楽しく働く”がもたらす、心と体の本質的充実
働くことと健康はどう結びつくのか?
東京都江東区の小さな印刷会社で、筆者は1年半前からフレックスタイム制の仕事にチャレンジしました。「週5できちんと出社しなければ」「人並みにアウトプットしなければ」と考えていた時期は、些細なミスが気がかりで帰宅後も疲れが抜けにくかったものです。
ところが、「やる気が湧かない日は無理やり成果を出そうとしない」「昼休みに散歩してみる」「同僚と、しょーもないジョークを言い合う時間を作ろう」と方針を切り替えてから、根本的に“気力”も“体調”も上向き始めました。仕事の効率は落ちるどころか、逆にアイデアや創造性が冴え、自分の存在価値も再認識できる日々。つまり、楽しく働く工夫こそが、間接的に健康な体とバランスのとれた心を生み出すのです。
近年の人材マネジメント研究でも、モチベーションやワークエンゲージメントの高さと健康リスクの低さ、プレゼンティーズム(病気のまま出社して生産性が下がる現象)回避の関係が繰り返し示されています。実際、『幸福度の高い従業員は生産性が31%アップする』(経済産業省調査,2022)といった調査も。楽しく働くことは決して「気分の問題」などではなく、現実世界で計測可能な健康資本だと言えます。
“働く喜び”はご褒美とセットに
さて、長期的に「楽しく働く」を持続可能にするための一つのコツ。徳島県のある介護士チームが毎月、少し気合の入るイベントを設け、「月末には好きなカフェのチーズケーキをテイクアウトする」「新作映画を見に行く」といった“自分にとってのご褒美タイム”を必ずセットしていました。リーダーが「ご褒美がなければ人間は頑張れないもの。達成感だけでなく、純粋な楽しみを体験として刻むのがコツ」と言うように、仕事と報酬は常に一対です。
自己犠牲や義務感だけに頼るのは、あくまで短期的なモチベーション維持に過ぎません。たとえ小さなご褒美であっても(500円のコンビニスイーツや、新しい文房具を買う喜びでも良い)、必ず「自分自身が欲しがる何か」を明確に意識して行動しましょう。家族やパートナーとの関係にも“ご褒美”の概念は重要で、互いに相手の努力や成長に拍手を送るような時間を意識的に作ると、チームワークや絆の深まりが実感しやすくなります。
“病気と寿命”という感覚の再定義
端的な話ですが、私の祖母は長野県の寒村で95歳まで畑仕事と釣りを楽しみ、体力が衰えるまで「どうせ寿命なんだから」と肩肘張らず日々を満喫していました。30代で一度大病を経験後も「医者なんかはうまく使うもので、自分で気に病んでちゃ何も始まらないよ」と笑い飛ばしていたのが印象的です。
死亡原因を見ても日本人の平均寿命が右肩上がりで延伸している現代、長生き=病気や不安が“無くなる”こととは全く別です。むしろ“どう生きるか”により一層の自由度が求められる時代。「老い」や「健康不安」に過度に囚われて人生の幅を狭めるのは本当にもったいない――。寿命と病気は必ずしもイコールではないという哲学を、一人ひとりの日常に落とし込んで広げていきましょう。
世界の成功者や知恵者は健康・働き方をどう考えてきたか
幸せ・長寿の裏にある共通点
世界中で大きな偉業を成し遂げた人々を調べてみると、必ずしも「健康体・病気知らず」という人ばかりではありません。フランスの文豪アンドレ・ジッドは幼少期から肺病を患いながらも、晩年まで創作を止めることなく活躍し続けました。彼が日記に繰り返し書いていたのは「自分の好きなことで頭をめぐらす時間が、何より体調維持に役立つ」という旨の記述です。
スペインのある陶芸家は、60歳のときに一度倒れた後、「やりたいことだけを無理せず、好きな仲間たちとやれる範囲で淡々と続ける」方針に変えてからむしろ作品の評価が高まったと語ります。健康を気にして好きな仕事をセーブした時期ほど調子が悪かったそうです。
なぜ日本人は「成功は後ろめたいもの」と思いがちなのか
日本に根強くある“成功者=何か裏がある”という雰囲気。それは子どもの頃から「人より良い思いをするのはわがままなこと」「出る杭は打たれる」的な価値観が刷り込まれているせいかもしれません。筆者も北海道の公立中学時代、成績がいい子や習い事で活躍する子が仲間内から嫉妬されがちな風土を感じていました。
一方、アメリカ西海岸の起業コミュニティでは、「成功した者が新たな価値や寄付を生むからこそ、みんなで応援し、称える」文化が強くあります。自分が力をつけて幸せになることが、地域や社会全体を恵ませる――こうした連鎖を意識できると、働くこと・挑戦すること・豊かになることへの罪悪感が消え去ります。
“寄付”や“お返し”の精神と豊かさの関係
ユダヤ教社会における「収入の一部を寄付する」という仕組みはよく文献でも目にします。筆者も一度、イスラエルの小規模企業を取材する機会を得ましたが、社長は「寄付やボランティアが一つの誇りであり、事業を伸ばすことへポジティブに関わる」と語っていたのを思い出します。
こうした哲学を知ると、「欲望を棄てて節制だけに走る」だけでは本当に豊かにはなれない、と自覚できます。むしろ、成果を分かち合う・お返しする喜びを自分のモチベーションに昇華する。「自分の成功も周りの豊かさも両方叶えてよい」というバランス感覚こそ、健康や仕事への取り組みにも直結するのです。
「今」を肯定する鈍感力と、“本との出会い”の効用
結局、「人生のどこ」を大切にできるか
一橋学園駅近くの小さなブックカフェで、たまたま耳にした言葉――「幸せは遠い未来のご褒美じゃなく、いま満たされていることに気づいた瞬間にある」。耳慣れたフレーズですが、実際どっしりと日常に落としこめている人は極めて少数です。
筆者自身、20代後半に“海外移住してみれば違う人生が拓けるかも”とスペイン・バルセロナに渡った経験があります。その町でパン屋を営む高齢夫婦は、「この町に一度も出たことがない」と胸を張っていました。「ここが好きだから、無理にどこか高望みするより目の前の暮らしを愛しているんだよ」。ふと自分の“もっと、もっと”という焦燥が溶け、自宅でコーヒーを飲むだけの朝にも無限の豊かさがあると気付いたのです。
いうなれば、「今ここで、楽しく働く・暮らす」を徹底的に肯定できる「鈍感力」。健康不安も自己実現も、すでにあるものに目を向ける習慣が、心身のブレない軸を生みます。
古典・物語がもたらす視点の多様化
どうしても心配や不安が拭えないとき、古き良き本や異なる価値観の物語にふれることが有効です。四国・松山市の図書館で開催された読書イベントで、ある女性が「荘子」「老子」を繰り返し読んでいると話していました。「政治的成功を断り釣りを続ける話や、泥の中を生きるどじょうのような人生観にふれると、他人の基準や社会の価値観からふっと解放される」と。実際漢文学者や東洋思想の研究者も、「人の幸せにひとつの正解はない」ことを諄々と古典に学んできた歴史があります。
また、経済小説やビジネス書でも、「成功は目的じゃなく過程そのものが面白い」というスタンスを描いた作品が多いです。例えば『新史 太閤記』や『ゲームの達人』の中には、困難をチャンスと捉え、目の前の工夫や遊び心によって活路を見いだす人物が描かれています。読書を通じて得られるこうした“他者の人生・価値観を疑似体験する時間”は、日常への柔軟さや「よそ見しても良いのだ」という許容力の育成に役立つのです。
実際に読書の習慣ができてから、自分自身「他人との比較」「健康不安」や「先行きの心配」から距離を置けるようになりました。本は生活や働き方に多層的なヒントを与えてくれる不可欠なツールです。
不安を手放し、“楽しく働く”日々を創る実践ガイド
1. 小さな「楽しみ」の種を毎日に入れる
朝、豆からコーヒーを淹れる・通勤途中に好きな花をひとつ見つける・仕事ファイルにお気に入りのシールを1枚貼るだけでも、「自分の暮らしに喜びを挟む」だけで気分のベースが変わります。この体感は決して侮れません。実際、都内在住の主婦グループが“1日1プチ喜び日記”をSNSでシェアしてから自己肯定感がアップし、家族の中でも会話が増え、夫婦ゲンカも減ったとリアルな報告もいただいています。
2. ご褒美システムを自作する
どんな仕事や家事の中にも、自分なりの「達成したらコレ」を用意しましょう。たとえば「水曜日はデザート解禁」「月末は本屋で新刊本を2冊好きに買う」「仕事帰りはいつもと違う道を散歩」。このささやかなご褒美が次の活力となって巡るため、意外にも疲労感も自然と軽減されていきます。
3. 成功・豊かさを「シェア」して広げる
社内で良かったことを同僚と褒め合う/できたことを家族に報告する/小さな寄付やプレゼントを定期的にする――自分の恵みを分かち合う時間は、結果的に自分への信頼や社会からの信頼感もアップします。自宅に小さな募金箱を置く、余ったおかずをシェアするだけでも効果を実感できますよ。
4. 健康診断や検査は“情報”として淡々と受け取る
検診結果に一喜一憂せず、あくまで自分の「今」を知るためのデータとして捉えるクセづけも大切です。糖質制限や運動も「生活に潤いをプラスする感覚」で楽しむほうが、ストレスなく続きます。筆者も年1回の検診日は必ず好きなカフェで自分をねぎらうことにしています。
5. 月に一冊、新しい本や古典に触れる
困ったとき、悩んだときは迷わず図書館へ。ジャンルを問わず、今まで手に取らなかった本や昔の物語、新進作家のエッセイでも良いのです。「今ここ」から視野を拡げ、人生を相対化できる新たな視点を育ててくれる小さな投資、それが読書の醍醐味です。
日々を軽やかにする“働きすぎ・心配しすぎ”との付き合い方
働くことも健康管理も、時代とともに変わり続けるもの。今の常識が明日もベストとは限りません。筆者自身、過去の栄養指導講座で「牛乳はいつでも最高の健康食」と言われた後、近年は「取りすぎはよくない」と勧められるなど、専門家の間でも流行が移り変わっています。
でも、本当に大切なのは「自分と周囲の体感」から生み出される知恵や快さ。極端なルールや他者の基準に頼り切るのではなく、「ちょっと肩の力を抜いた自分らしい過ごし方」にシフトする。そのためには、自分の楽しいこと・気持ちが晴れる時間を大切にする。心配しすぎたなと気づいたときは、「またやっちゃった」と笑えるくらいの余裕で受け流す――。そんなライトな“自己許容”が、結果人生のクオリティを底上げするコツだと実感しています。
うまくいかない日や体調が崩れるときも、「健康や幸福とは、完璧な状態のことじゃなく、ちょっとズレたり凹んだりを面白がることかも」と考えてみる。まじめな人ほど“心配しすぎる自分”も笑いのタネにして、同僚や友人とシェアしてみる。体の不調や不運も、長い人生の“味”として気楽にやりすごしてみてください。
まとめ:健康と豊かさ、その本当の核心に目を向けて
健康診断や病気の不安に敏感になりがちな現代社会。本当に“心身ともに満たされた豊かな毎日”にたどりつくためには、「楽しく働き、日常にご褒美や喜びを丁寧に設けること」が最も着実で確実な方法かもしれません。身近な人々、世界の成功例、本や物語……すべてが「今ここを大切にしよう」と語りかけています。
健康や幸せは“情報”や“他人の価値観”に振り回されるほど遠のいていくもの。自分の気持ちに正直に、一歩一歩、小さな「楽しい」「嬉しい」を重ねていく。その結果として、不安よりも軽やかな心・より自由な人生を手に入れることができるはずです。
明日からの一日、ちょっと肩の力を抜いて、「楽しく働く」ことを土台にした暮らしを試してみませんか? 世界のどこを探しても、これに勝る健康法と豊かさの秘訣は、他にないのですから。